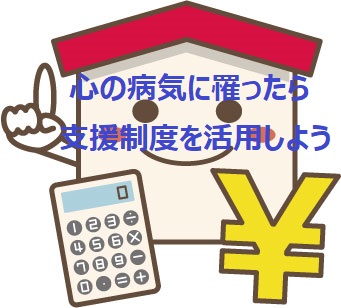こんにちは、株&不動産投資家 兼 サラリーマンのトムです。
さて今回はタイトルにある通り、心の病気を患っている方が受けられる支援制度について解説していきたいと思います。
私はプロフィールにもある通り2020年にうつ病を患っており、未だに完治していません。現在は月2回の心療内科への通院と服薬を続けています。そんな私が病気を患ってから知ったことは、うつ病をはじめとした精神障害者への自治体・事業者の支援制度が充実しており、マネーリテラシーの観点では知っておかないと逆に損になり得ます。私自身がその支援を受けておりますので今回解説しようと思いました。
なお1点お断りですが、本記事は私の住んでいる神奈川県横浜市の制度をベースとしております。各自治体・事業者によってサービス内容が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体のウェブサイト等をご確認下さい。
身近になりつつある「心の病気」
最近、著名人・有名人が心の病気を患ったというニュースをたびたび目にしませんか。思いつくだけでも以下の件が挙げられます。
- テニスプレイヤーの大坂なおみ選手がうつ状態を告白
- 東京五輪で女子体操のシモーン・バイルス選手(米国)が心の健康をめぐり演技を欠場
- King & Princeの岩瀬さんがパニック障害の治療に専念することを理由にグループ脱退
- 女優・深田恭子さんが適応障害で女優業を3か月間休業
- 秋篠宮眞子様が複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を患っていることを宮内庁が発表
いま日本では心の病気に罹る方が急増しています。
下のグラフは厚生労働省が発表している「心の病気」の患者数の推移と年代別割合になります。上半分の棒グラフの中で青色の「気分障害など」がうつ病・躁うつ病の患者を含む分類になり、グラフを見て分かるように近年その数は増加傾向です。
また気分障害の年代別割合を見てみると、働き盛りである30~50歳代および65歳以上の割合が大きいですが、どんな年齢でも罹患する可能性があると言えます。
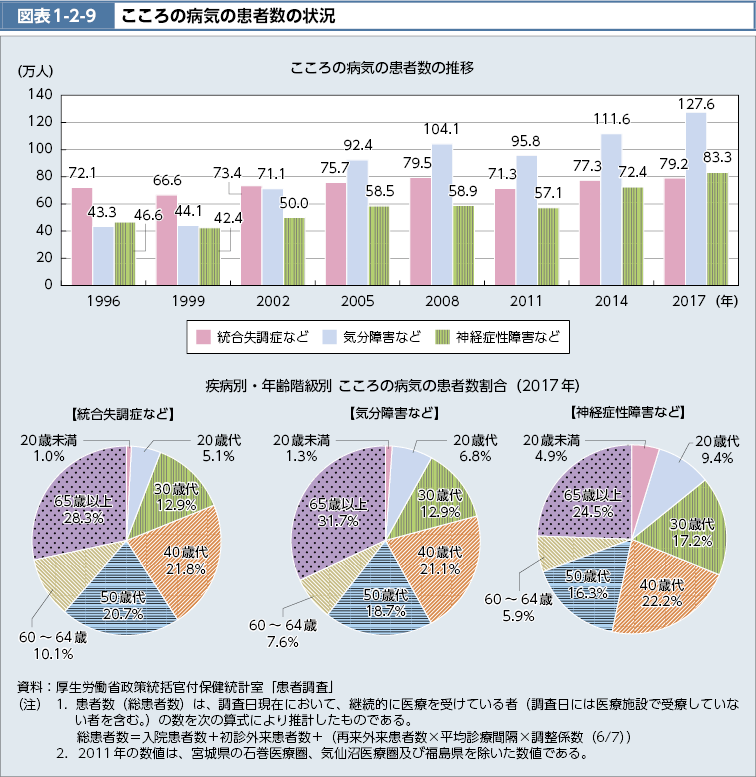
このように近年では著名人・一般人に関係なく心の病気を患う方が増加傾向にあり、心の病気は徐々に私たちの身近なものになりつつあると言えます。
精神障害者が受けられる支援制度
精神障害の種類
さてそんな心の病気を患った方が受けられる支援制度を紹介していきます。まず初めに支援制度の対象となる心の病気=精神障害の種類ですが、厚生労働省のサイトによると以下の通りです。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
支援を受けるために必要なもの
支援を受けるために必要なものは、①精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)と、②自立支援医療受給者証(精神通院医療)の2つになります。
精神障害者手帳は一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものであり、支援を受けるためのパスポート的な位置づけのものになります。以下の表のとおり、障害の程度により1級~3級の等級に分かれます。
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
今回は主に私が認定を受けている2級について解説します。なお2級と3級の支援内容に大きな違いはありません。1級は障害が非常に重く、2級・3級と比べて支援が手厚くなります。
そして②自立支援医療受給者証(精神通院医療)は精神障害者手帳とは別もので、 「自立支援医療制度」における支援を受けるために必要です。後ほど解説します。
上記2つの入手方法は、主治医に診断書を記入してもらい各自治体の対象窓口に申請するのが基本となります。なお自治体によっては1種類の診断書で上記2つの両方を一度に申請できる場合があります(神奈川県ではこちらのサイトにある診断書の利用で可能)ので確認をしてみてください。申請に必要な期間については、私のケースですと窓口に申請してからおおむね1か月で手帳と受給者証の交付を受けられました。
自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療制度 (精神通院医療) は精神障害により継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方向けの支援制度で、 自立支援医療受給者証(精神通院医療)が必要です。支援内容は以下の2点です。
- 医療費の自己負担が原則1割になります(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外)
- 所得水準に応じて負担の上限額が設定されます
私の住む横浜市での自己負担の上限額はこちらのサイトで解説されております。市民税の納付額によって負担の上限額が変わってくる点と、「重度かつ継続」(高額治療継続者)と認定された場合にも上限額が設定されている点がポイントです。
自己負担が1割というのは家計的に大きいです。私の場合ですと認定前は月2回の通院で自己負担額が6,000円程度でしたが、今は2,000円程度に削減できました。
所得税・住民税の障害者控除
所得税、住民税のそれぞれで、課税所得に対して障害者控除を受けられます。障害者控除の金額は以下の通りです。
所得税・住民税には様々な所得控除項目があります(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)が、障害者控除も控除額は小さくなく、家計的には大きく影響がありますね。私はサラリーマンですので(おかしな話かもしれませんが)いまから年末調整が楽しみです(^^;
一部の公共交通機関を無料で利用できる
横浜市では精神障害者1級~3級の方向けに「福祉特別乗車券」の交付が受けられます。利用者負担金として年額1,200円が必要ですが、横浜市内の路線バス、横浜市営地下鉄全線の利用が無料になります。どの交通機関でもおおむね片道200円は掛かりますから、6回乗ったら元が取れます。
2020年から2021年はコロナ禍で公共交通機関の利用がめっきり減っていましたが、9月末に緊急事態宣言が解除されました。なのでこれからは少しずつ外出の機会が増えていきますし、この福祉特別乗車券の利用頻度も上がっていくと思います。しっかりと活用したいと思います。
公的な支援制度を上手に活用し、家計を改善させよう
今回は精神障害者の方が受けられる支援制度について解説しました。
- 支援を受けるためには、①精神障害者手帳の交付と、②自立支援医療受給者証の交付を受ける
- 主な支援は以下の3つ
- 自立支援医療制度(医療費の自己負担が原則1割 負担額の上限あり)
- 所得税・住民税の所得控除(所得税は27万円控除 住民税は横浜市の場合26万円)
- 一部の公共交通機関を無料で利用できる
障害者向けの支援に限った話ではありませんが公的な支援制度を利用するには、まず内容を理解して、自治体窓口に申請することが必要です。もし私と同じようにうつ病に苦しまれていて、上記の支援制度を利用されてない方は、すぐにでも利用してみることをお勧めします。
今回は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。